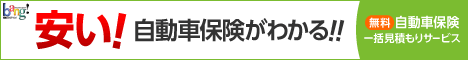もくじ
【完全ガイド】車の保険料を経費にして、賢く税金を抑えよう!
個人で仕事をしている人(個人事業主やフリーランス)や、会社を経営している人にとって、車にかかるお金、特に「自動車保険料」をどこまで経費にできるかは、とても重要な問題です。
「経費にする」とは、仕事で使ったお金を事業の支出として計上すること。経費が増えれば、そのぶん利益(所得)が減り、結果的に支払う税金が少なくなります。
この記事では、自動車保険料を経費にするための基本ルールから、プライベートと仕事で車を兼用している場合の計算方法「家事按分」、税務署にチェックされるときの注意点、具体的な計算例、そして節税に役立つポイントまで、知っておくべきこと全てを、誰が読んでもわかるように解説します。
この知識をしっかり身につけて、正しく経費を計上し、賢く節税につなげましょう!
自動車保険を経費にするための基本ルール

まず、一番大切な大原則から確認しましょう。それは、「自動車保険料は、事業(仕事)のために使用した分だけ経費にできる」ということです。完全にプライベートでしか使わない車の保険料は、仕事と関係がないので経費にすることはできません。
この基本ルールは、個人で仕事をしているか、会社(法人)として事業を行っているかで、少し扱い方が変わります。
個人事業主・フリーランスの場合
自分の車(自家用車)を仕事にも使っている場合、その仕事で使った割合分だけを経費にできます。例えば、商品を運んだり、打ち合わせ先に行ったりするために車を使うケースです。
もし、仕事でしか使わない専用の車があるなら、保険料は全額経費にできます。しかし、多くの人は買い物などのプライベートな用事と仕事を一台の車で兼用しているはずです。その場合は、後で詳しく説明する「家事按分(かじあんぶん)」という計算が必要になります。
また、個人事業主には「青色申告」と「白色申告」という確定申告の方法があります。しっかり帳簿をつける必要がある「青色申告」をしている人は、仕事で使う割合が半分(50%)以下でも、その割合に応じて経費にすることが認められていま。一方、「白色申告」の人は、仕事での使用がメイン(目安として半分以上)でないと経費として認められないことが多いので、注意が必要です。
法人(会社)の場合
会社名義の車を事業のために使っているのであれば、自動車保険料はもちろん、ガソリン代や税金などの関連費用は、基本的に全額を経費にできます。
ただし、注意点が一つ。会社の車であっても、社長や社員がプライベートな旅行や買い物で使った場合、その分は経費にできません。もし、プライベートでの利用が税務署に見つかると、その分は経費として認められず、追加で税金を支払うことになる可能性があるので、きちんと区別する必要があります。
経費にするときの「勘定科目」は?
帳簿につけるとき、経費を分類する名前を「勘定科目」といいます。自動車保険料は、個人事業主なら「損害保険料」や「車両費」、法人なら「支払保険料」や「車両費」といった勘定科目で処理するのが一般的です。どの科目名を使うかは厳密に決まっていませんが、一度決めたら毎年同じ科目名を使い続けるのがルールです。
「家事按分」をマスターしよう!仕事とプライベートの分け方

家事按分って、そもそも何?
「家事按分(かじあんぶん)」とは、一つの支出の中にプライベート(家事)で使った分と、仕事(事業)で使った分が混ざっている場合に、仕事で使った分だけを計算して経費にする手続きのことです。
これは車だけでなく、例えば以下のようなケースで使われます。
- 自宅兼事務所の家賃や光熱費: 家の一部を仕事場として使っている場合。
- 個人のスマホ代やネット代: プライベートと仕事で同じスマホや回線を使っている場合。
自家用車を仕事にも使う場合は、保険料やガソリン代、税金といった車関連の費用を、この家事按分を使って「事業分」と「私用分」に分ける必要があるのです。
どうやって割合を決めるの?具体的な計算方法
税金の法律で「計算式はこれ!」と細かく決まっているわけではありませんが、誰が見ても「なるほど、合理的だね」と納得できる基準で計算する必要があります。車の場合は、主に2つの基準が使われます。
走行距離で分ける方法
仕事で走った距離と、プライベートで走った距離の割合で計算します。これが一番わかりやすく、説明しやすい方法です。
(計算例)
年間の総走行距離が10,000kmで、そのうち仕事での移動が8,000kmだった場合。
-
- 事業利用の割合: 8,000km ÷ 10,000km = 80%
-
-
- この場合、年間の自動車保険料の80%を経費として計上できます。
-
使った日数や時間で分ける方法
車を仕事で使った日数と、プライベートで使った日数の割合で計算します。
(計算例)
1週間のうち、月曜から金曜の5日間は仕事で使い、土日の2日間はプライベートで使う場合。
-
-
-
- 事業利用の割合: 5日 ÷ 7日 ≒ 71%
- この割合を、保険料などの費用にかければ、経費にできる金額が計算できます。
-
-
どちらの基準を使うにしても、大切なのは「なぜこの割合になったのか」を説明できる記録を残しておくことです。
税務署にチェックされても慌てない!経費計上の注意点

経費の計算を間違えたり、ルールを無視したりすると、後から税務署に指摘されてペナルティを受ける可能性があります。そうならないために、以下の点に注意しましょう。
- 明確な根拠と証拠を残すこと!
税務署は「本当にその経費は事業に必要だったのか?」を厳しくチェックします。按分計算の根拠となる走行距離のメモや業務日誌、そして領収書などは、必ずセットで保管しておきましょう。書類の保管期間は、白色申告で5年、青色申告で7年が義務付けられています。
- 経費の盛りすぎは絶対にダメ!
節税したいからといって、実際の仕事での利用割合よりも高く設定するのは危険です。もし実態と違うことがバレると、その経費が全額認められなくなるリスクもあります。正直に、実態に合った割合で計算しましょう。
- 少しでもプライベートで使ったら按分は必須!
「ほとんど仕事で使っているから」という理由で、100%経費にするのは間違いです。少しでもプライベートで利用しているなら、必ず家事按分を行ってください。
- 【法人向け】会社の車のプライベート利用は特に注意!
先ほども触れましたが、社長や役員が会社の車をプライベートで使うと、その費用は「会社から役員への給料(役員賞与)」と見なされることがあります。そうなると、会社は経費にできず、役員個人の税金も増えるという二重のペナルティにつながる可能性があります。対策として、プライベートで使った分は、個人が会社に「使用料」として支払うなどのルール作りが必要です。
もっとお得に!賢い節税対策のポイント

ルールを守りつつ、節税効果を最大化するための工夫をいくつかご紹介します。
- 車に関する費用は、もれなく経費に!
自動車保険料だけでなく、ガソリン代、オイル交換などのメンテナンス費用、タイヤ代、駐車場代、高速道路料金、自動車税など、車にかかる費用はたくさんあります。これらもすべて家事按分して、忘れずに経費に計上しましょう。 - 按分率は「適切」かつ「有利」に設定しよう
自分の仕事の実態をきちんと記録し、正当に主張できる範囲で、最も有利な基準(例えば、走行距離と日数の両方を計算してみて、合理的な範囲で割合が高くなる方)で按分率を計算するのも一つの手です。 - 「青色申告」を活用しよう!
個人事業主の場合、帳簿付けは少し大変になりますが、「青色申告」には税金が安くなる特典がたくさんあります。最大65万円の特別控除だけでなく、家事按分でも有利な扱いを受けられるので、まだ白色申告の人は青色申告への変更を強くおすすめします。 - 「事業専用の車」を用意する
もし資金に余裕があれば、プライベート用と仕事用で車を完全に分けてしまうのも非常に有効な節税策です。事業専用の車にかかる費用は、ほぼ100%経費にできるため、面倒な按分計算から解放されます。
最新のルールや今後の動向について

最後に、最近の税金のルール変更などについて触れておきます。
- 直近の税制改正の影響
2023年や2024年の税制改正では、自動車保険料の経費計上や家事按分のルール自体に大きな変更はありませんでした。これまで通りの考え方で大丈夫です。 - デジタル化への対応(インボイス制度など)
2023年10月から始まったインボイス制度により、領収書などの書類管理がより重要になっています。自動車保険料は消費税がかからない(非課税)取引ですが、車の修理代やガソリン代には消費税がかかるため、インボイスに対応した領収書をもらう必要があります。また、法律の改正で領収書などを電子データ(スマホの写真など)で保存することも認められていますので、上手に活用しましょう。 - 税務調査のトレンド
最近の税務調査では、個人事業主や会社オーナーのプライベートな経費が事業の経費に混じっていないか、という点が厳しくチェックされる傾向にあります。だからこそ、日頃から公私をしっかり分け、記録を残しておくことが、何よりの防御策になります。 - 将来の方向性
今後も、「事業に直接必要な経費だけを認める」という税金の基本原則が変わる可能性は低いです。安心して、このルールに沿って経理処理を行いましょう。
まとめ

自動車保険料を経費にするためのポイントを、もう一度おさらいします。
- 基本原則: 仕事で使った分だけを、しっかりとした根拠をもって経費にする。
- 家事按分: プライベートと兼用している場合は、走行距離などの合理的な基準で計算する。
- 記録と証拠: 計算の根拠となる記録や領収書は、5年~7年間、大切に保管する。
- 賢い節税: ルールの範囲内で、計上できる経費をもれなく計上し、税金の負担を正しく最適化する。
一番大切なのは、
「事業に使った分だけ、根拠をもって経費にする」
ということです。経費を正しく計上することは、事業を行う人の正当な権利です。公私の区別をしっかりつけ、誰に見られても恥ずかしくない、信頼性の高い申告を心がけましょう。この記事が、あなたのビジネスに役立てば幸いです。